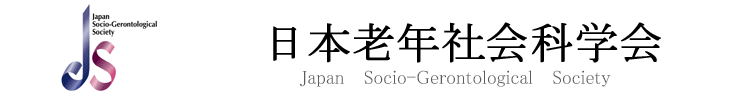- 老年社会科学 2025.10 Vol.47-3
- ↑トップページへ戻る
| 論文名 | 令和6年能登半島地震応急期における高齢者に関する避難所の実態 |
| 著者名 | 有吉恭子 |
| 雑誌名 巻/号/頁/年 |
老年社会科学,47(3):332—338,2025 |
| 抄録 |
本研究は,令和6 年能登半島地震における石川県輪島市の一般の指定避難所を対象に,応急期における高齢者の避難生活実態を明らかにすることを目的とした.災害対策本部事務局の運営支援における参与観察および後日の避難所担当職員・避難所施設管理者への聞き取り調査を通じて,高齢者特有の課題と現場で生まれた支援の工夫を明らかにした. 調査の結果,応急期の避難所で高齢者が直面した課題としては,①情報伝達の混乱と集落の孤立,②避難所空間の段差や設備不備,③トイレ・衛生管理と失禁,④精神的負担が確認された.課題に対しては,まずは,避難所内での助け合いによる工夫と,医療・保健の外部支援団体が対応し,発災から約20 日後,市役所から調査・情報収集のち,改善が図られた.医療・保健の外部支援内容が,住民主体の行動に継続される前向きな事例もみられた.本研究は,今後の高齢者支援や避難所運営,受援体制設計に重要な示唆を与える. |
| キーワード | 能登半島地震,高齢者,避難所環境,災害応急期 |
| 論文名 | 地域在住認知症等要支援高齢者を守る災害準備と支援体制――安否確認から生活継続支援まで―― |
| 著者名 | 涌井智子 |
| 雑誌名 巻/号/頁/年 |
老年社会科学,47(3):339—345,2025 |
| 抄録 | 本稿は,日本の超高齢社会における地域在住認知症等要支援高齢者を対象とした災害対策の必要性と課題を論じた.人口高齢化の進展,認知症を含む健康上の脆弱性,そして自然災害の激甚化という三重の課題は,従来の枠組みを超えた新たな支援体制の構築を迫っている.過去の大規模災害を契機に制度や地域支援体制は整備されつつあるが,在宅で暮らす高齢者の備えは依然として限界がある.とくに,発災時の安否確認や避難支援を実効性あるものとするためには,公的制度に基づく名簿整備や福祉避難所の運用に加えて,家族・地域住民・専門職の協働による多層的な支援ネットワークが不可欠である.さらに,災害直後の命を守る対応にとどまらず,中長期的に生活の継続とケアを支える視点を組み込むことで,社会全体として持続可能なレジリエンスを高めることが求められる. |
| キーワード | 災害準備,認知症,要支援,要介護,自助,公助,安否確認 |
| 論文名 | 認知加齢の個人差の理解に向けて:環境・動機・行動の視点から |
| 著者名 | 石岡良子 |
| 雑誌名 巻/号/頁/年 |
老年社会科学,47(3):346—352 ,2025 |
| 抄録 | 長寿社会における高齢期の認知機能の維持は,個人の尊厳や社会的自立の観点から重要な課題である.本稿では,認知機能と生活環境の関係について,行動学と神経心理学の両面から検討したうえで,ライフコースにおける環境要因の影響を概観する.そして,幼少期から高齢期までの経験が,どのように認知機能の保持や認知症リスクの低減に関与するか観察研究の知見を整理し,個人差の背景を探る.また,行動の継続や般化を促す心理的要因として,成長マインドセット,自己決定理論,フロー理論などを紹介し,内的動機づけや感情経験が,認知的に高度な処理を求められる環境への志向や継続性を支える可能性を論じる.これにより,認知的刺激に富んだ環境を生涯にわたり維持するプロセスの理解が深まることを期待する. |
| キーワード | 認知機能,生活環境,ライフスタイル,ライフコース |
| 論文名 | 高齢者研究における筆記表現法の活用と課題 |
| 著者名 | 小川 将 |
| 雑誌名 巻/号/頁/年 |
老年社会科学,47(3):353—360,2025 |
| 抄録 | 加齢に伴い人生経験が豊かになる一方,喪失体験をはじめとするネガティブなライフイベントも蓄積される.筆記表現法は喪失体験と心身の健康の関連から着想を得た介入法である.ネガティブな出来事を1日約15 分,紙に書き出すことで心身の健康の向上に寄与することが報告されており,これまで大学生を対象とした豊富な研究蓄積がある.しかしながら,筆記表現法の介入効果は小さい.また,高齢者を対象とした場合には遵守率・脱落率などの課題がある.これらの課題を乗り越えるためには,筆記表現法の諸理論に基づき,「対象・介入内容・アウトカム」を一致させることが重要である. |
| キーワード | 筆記表現法,ストレス,トラウマ,ライフイベント,ライフレビュー |
| 論文名 | 身体機能や社会的機能が変化するなかで,高齢者はこころの健康をいかに維持しているのか |
| 著者名 | 深瀬裕子 |
| 雑誌名 巻/号/頁/年 |
老年社会科学,47(3):361—365,2025 |
| 抄録 | 高齢期には身体機能や社会的役割の変化が生じやすいが,多くの高齢者はそれらの変化にうまく適応し,心理的な健康を保っている.本稿では,筆者が実施した3 つの研究を紹介し,その背景にある適応の力について考察した.第1 の研究では,身体的自立度の高い高齢者にとっては「老いの受容」よりも「主張性」が主観的幸福感に寄与する可能性が示された.第2 の研究では,パンデミックによって身体機能や認知機能は低下したが,精神的健康は維持されていたことが示された.第3 の研究では,「感情表出」や「肯定的再解釈」といった対処法が高齢者の抑うつ軽減に有効であり,その使用頻度は若年層より高いことが示された.これらの結果から,加齢や環境の変化に柔軟に対応する力こそが,こころの健康を支える重要な要素であることが示唆された. |
| キーワード | 高齢者,心理的健康,適応力,対処方略,臨床心理学 |